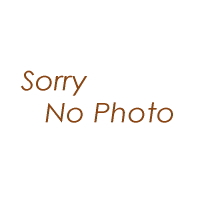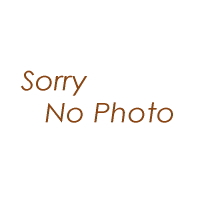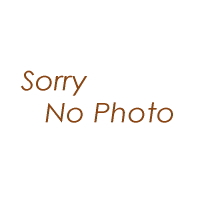JR2(その他の直流電車、交流・交直流電車、気動車の走行音)
このページでは、通勤型・近郊型以外の直流電車、交流・交直流電車、気動車の走行音を公開しています。
↓直流通勤型・直流近郊型はこちらへ。
JR1(直流通勤型、直流近郊型電車の走行音)
↓新幹線はこちらへ。
JR3(新幹線の走行音)
・近郊型(交流・交直流)…403系(全廃) 415系 417系 E531系 719系 E721系 811系 813系 815系 817系
・急行型…167系(全廃) 455系(全廃) 475系
・特急型…183系(全廃) 185系 189系(全廃) 251系 255系 E257系 E259系 E351系(全廃) 371系 373系 651系 E653系 E657系
・気動車…キハ40系 キハ58系 キハ11系
403系
(全廃) |
 |
| 抵抗・120KW |
| 製造初年:昭和40(1965)年 |
国鉄近郊型の交直両用バージョンで、交流50Hzのみ対応のもの。MT46を採用した401系の増備車でMT54を採用した車両。増備は早い時期に交流 50Hz・60Hz両対応の415系に移行したため少数の増備にとどまった。最終編成のみ押込型通風器を採用したが、他はグローブ型である。当初非冷房であったがのちに冷房化され、全車JR東日本に引き継がれた(一部に冷改を受けることなく廃車になった編成もある)。当初より晩年に至るまで常磐線、水戸線で使用されてきたが、老朽化とE531系導入のため、2007年3月をもって全車廃車となった。
| 車両番号:モハ403-7(廃車) |
種別・行先:普通 土浦 |
収録区間:ひたち野うしく→土浦 |
| 最高速度:95km/h |
マイク:CM-S330 |
収録日:'07.1.25録音 |
音(YouTube) 9:57  |
音は115系などと同じです。
このページの一番上へ↑
| 415系 |
 |
| 抵抗・120KW |
| 製造初年:昭和46(1971)年 |
国鉄近郊型の交直両用バージョンで、交流50Hz・60Hz両対応のもの。セミクロスの0番台、そのシートピッチ拡大車100番台、ロングシートの 500番台、211系と同一の車体である1500番台がある。JR化後はJR東日本とJR九州の2社に引き継がれた。JR九州では在籍する唯一の交直両用近郊型電車となっており、関門トンネルを走行する普通列車の全列車を担当しているが、他線区では新型車両が続々と製造され、朝夕ラッシュ時のみ細々と運転されている。JR東日本では常磐線E531系の導入により廃車が進み、鋼製車は2007年3月をもって全廃となった。残された1500番台も2016年3月をもって全編成が運用を失い、JR東日本からは消滅した。なお、JR西日本では113系の交直流化改造車が415系800番台を名乗っている。
| 車両番号:モハ415-121(廃車) |
種別・行先:普通 土浦 |
収録区間:我孫子→藤代 |
| 最高速度:100km/h |
マイク:CM-S330 |
収録日:'07.1.18録音 |
音(YouTube) 12:52  |
113系や115系と同じ音です。常磐線の東京近郊区間で最後の活躍をする鋼製車の走行音です。
このページの一番上へ↑
417系
(全廃) |
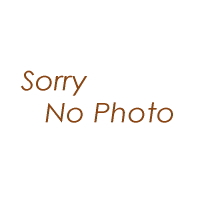 |
| 抵抗・120KW |
| 製造初年:昭和53(1978)年 |
東北地方の輸送改善用に製造された2扉車セミクロスシートの交直両用近郊型電車。空気バネ台車を装備している。3連5本のみと、少数の増備にとどまった。一時期仙山線作並以東の列車にも使用されたが、それ以外は仙台地区の東北本線の列車のみに使用され、交直両用(50Hz、60Hz両対応)電車でありながら、60Hz区間や直流区間を営業運転したことは一度もなかった。2007年7月をもって全車運用を離脱、1本が阿武隈急行に譲渡されたが、他は全車廃車となった。
| 車両番号:モハ416-4(廃車) |
種別・行先:普通 松島 |
収録区間:陸前山王→国府多賀城 |
| 最高速度:80km/h |
マイク:CM-S330 |
収録日:'02.1.1録音 |
| 音(mp3) 1:53 2.60MB |
主電動機は113系と同じMT54ですが、かなり静かです。かろうじて音程だけが113と同じ・・・。
このページの一番上へ↑
| E531系 |
 |
| VVVF(IGBT)・140KW |
| 製造初年:平成17(2005)年 |
つくばエクスプレスに対抗するための常磐線のスピードアップと、老朽化した403・415系の置き換えのために製造された4扉の交直両用近郊型電車。設計最高速度はJR東日本の近郊型としては初めて130km/hとなり、実際に130km/hでの営業運転も行われている。足回りはE231系の95KWに対し140KWと強化され、歯車比もE231系の1:7.07から1:6.06と高速向けになった。これはE217系と同じ歯車比である。起動加速度は2.5km/h/sで近郊型としては高く、取手以南で活躍する通勤型E231系と同じ起動加速度となっている。制御装置は日立製。当初モノクラスであったが後にグリーン車も連結され、2007年3月の改正で上野口の中距離電車の全列車を受け持つことになった。同時に特別快速以外の列車も最高速度130km/h運転を行うことになった。なお、この系列は用途が限定されているため、E233系のように継続的には増備されていないが、上野東京ライン開業に伴う増発分や黒磯駅直流化に伴う黒磯~郡山間の列車への充当など、必要数に応じて少しずつ増備されている。
| 交流区間 |
| 車両番号:モハE531-7 |
種別・行先:普通 上野 |
収録区間:土浦→佐貫 |
| 最高速度:130km/h |
マイク:H1 |
収録日:'11.3.6録音 |
音(YouTube) 17:34  |
非同期音は東芝の音に近く、加速時の変調の仕方は三菱に近いです。純電気ブレーキ対応ですが、減速時の非同期音と停車寸前の音が連続的に聞こえるのが特徴的。牛久→佐貫では130km/h運転を行っているほか、土浦→荒川沖で125km/h、ひたち野うしく→牛久で120km/h近くまで加速するなど、全体的にハイペースでの運転です。
| 交流区間~交直切替~直流区間 |
| 車両番号:モハE531-7 |
種別・行先:普通(取手から快速) 上野 |
収録区間:佐貫→天王台 |
| 最高速度:125km/h |
マイク:H1 |
収録日:'11.3.6録音 |
音(YouTube) 12:26  |
直流区間では、加速時の変調のタイミングが交流区間に比べ早いです。藤代→取手では、125km/h程度まで加速しています。
このページの一番上へ↑
| 719系 |
 |
| サイリスタ位相・120KW |
| 製造初年:平成元(1989)年 |
東北地方の輸送改善(短編成・高頻度化)のため登場した2両固定編成の車両。全車が1M1Tの2両固定編成を組んでいる。近郊型ではあるが、歯車比は205系と同じ1:6.07で、走行音は205系内扇車と同じである。山形新幹線開業に伴う奥羽本線標準軌化に伴い、標準軌用の編成が5000番台として製造された。東北本線・常磐線(いずれも仙台地区)、仙山線、奥羽本線、磐越西線で活躍していたが、0番台はE721系1000番台に順次置き換えられ、廃車が進んでおり、東北本線と仙山線・磐越西線からは撤退している。
| 車両番号:クモハ719-3(廃車) |
種別・行先:普通 松島 |
収録区間:館腰→名取 |
| 最高速度:100km/h |
マイク:CM-S330 |
収録日:'02.1.1録音 |
| 音(mp3) 3:21 3.07MB |
モーター音は205系内扇と全く同じ。
このページの一番上へ↑
| E721系 |
 |
| VVVF(IGBT)・125KW |
| 製造初年:平成19(2007)年 |
仙台空港線開業用、および455系等旧国鉄急行型車両の置き換え用として製造された2両固定編成の車両。仙台空港線用ワンマン対応の500番台とそれ以外の路線で使用される0番台がある。現在、常磐線と東北本線の交流区間と仙山線で使用されている。2016年からは、719系0番台置き換え用の1000番台が製造された。1000番台は本形式初の4両固定編成となった。
| 車両番号:クモハE721-502 |
種別・行先:普通 仙台空港 |
収録区間:南仙台→名取 |
| 最高速度:100km/h |
マイク:DR-07 |
収録日:'09.10.19録音 |
| 音(mp3) 3:27 4.75MB |
モーター音はJR東海の313系と同じタイプ。
このページの一番上へ↑
| 811系 |
 |
| サイリスタ位相・150KW |
| 製造初年:平成元(1989)年 |
老朽化した421・423系の置き換えと列車のスピードアップのため福岡地区に投入された3扉転換クロスシート車。現在鹿児島本線門司港~荒尾間の普通・快速を中心に使用され、他線に入ることは少ない。
| 外扇 |
| 車両番号:クモハ810-111 |
種別・行先:普通 大牟田 |
収録区間:瀬高→南瀬高 |
| 最高速度:110km/h |
マイク:CM-S330 |
収録日:'04.2.19録音 |
| 音(mp3) 2:43 3.75MB |
阿武隈急行8100系とほぼ同じ音。JR201系と同じ音程。
| 内扇 |
| 車両番号:モハ811-111 |
種別・行先:普通 大牟田 |
収録区間:銀水→大牟田 |
| 最高速度:100km/h |
マイク:CM-S330 |
収録日:'04.2.19録音 |
| 音(mp3) 3:28 4.77MB |
静かです。たまたま同じ編成に2種類の音がありましたが、検査時に他の編成のものと入れ替わったのでしょう。
このページの一番上へ↑
| 813系 |
 |
VVVF(GTO)・150KW
VVVF(IGBT)・150KW |
製造初年:
平成6(1994)年(GTO)
平成17(2005)年(IGBT) |
老朽化した423系や415系の置き換えのため投入されたVVVF3扉転換クロスシート車。福岡地区を中心に普通列車・快速列車に使用されている。 811、815、817系との併結も可能。制御装置は東芝製でモーター出力は150KW。当初GTOであったが、平成17年の増備車からIGBTとなり、さらに平成19年の増備車からは行先表示器に大型LEDが採用されるなどマイナーチェンジされている。残念な事故により8両が廃車となったが、平成19年7月現在219両の在籍数を誇り、JR九州の所有の形式では最大勢力となっている。
| GTO |
| 車両番号:クモハ813-6 |
種別・行先:普通 荒尾 |
収録区間:南瀬高→渡瀬 |
| 最高速度:120km/h |
マイク:CM-S330 |
収録日:'04.2.17録音 |
| 音(mp3) 3:31 3.22MB |
低速向けの歯車比のためモーターの回転数が高め。811系との併結列車での収録です。
このページの一番上へ↑
| 815系 |
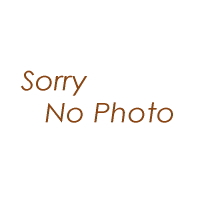 |
| VVVF(IGBT)・150KW |
| 製造初年:平成11(1999)年 |
豊肥本線熊本~肥後大津間電化に合わせ登場したワンマン対応2両固定の車両。JR九州オリジナルの近郊型電車としては唯一のロングシート車である。その後増備され、鹿児島本線鳥栖~八代間や日豊本線にも活躍の場を広げている。制御装置は日立製。
| 車両番号:車番不明 |
種別・行先:普通 八代 |
収録区間:荒尾→南荒尾 |
| 最高速度:110km/h |
マイク:CM-S330 |
収録日:'04.2.17録音 |
| 音(mp3) 2:57 2.70MB |
E231系近郊型の変調が遅くなったという感じの音です。
このページの一番上へ↑
| 817系 |
 |
| VVVF(IGBT)・150KW |
| 製造初年:平成13(2001)年 |
福北ゆたか線と愛称がつけられた筑豊本線・篠栗線の電化開業に合わせて新製されたワンマン対応2両固定の車両。転換クロスシート車である。その後、長崎本線・佐世保線にも投入されワンマン非対応である813系の運用を置き換えた。現在はさらに増備され大分地区・鹿児島地区でも使用されている。制御装置は日立製と東芝製が存在する。
| 日立 |
| 車両番号:クモハ817-1001 |
種別・行先:普通 直方 |
収録区間:小竹→勝野 |
| 最高速度:90km/h |
マイク:CM-S330 |
収録日:'04.2.18録音 |
| 音(mp3) 4:01 3.68MB |
815系と同じ音。
| 東芝 |
| 車両番号:クモハ817-30 |
種別・行先:普通 鳥栖 |
収録区間:肥前麓→鳥栖 |
| 最高速度:100km/h |
マイク:CM-S330 |
収録日:'04.2.17録音 |
| 音(mp3) 4:18 3.95MB |
東芝の走行音。
このページの一番上へ↑
167系
(全廃) |
 |
| 抵抗・120KW |
| 製造初年:昭和40(1965)年 |
165系の修学旅行バージョンとして、黄色とオレンジのツートンカラーで製造された車両。165系とは側扉の幅が異なっているほか、制御車と電動車のみのシンプルな組成で、Tc-M'-M-Tcの4両固定編成で登場した。登場後10年ほどで修学旅行の移動手段は新幹線や観光バスに移行。修学旅行専用車としての活躍期間は思いのほか短く、波動輸送用に転用された。全車非冷房で登場したが、のちに冷改、塗装も湘南色に変更された。JR化後はJR東日本とJR西日本に引き継がれ、東日本車は田町電車区に、西日本車は宮原運転所に配置された。晩年はJR東日本車を中心に再度塗装変更され、リクライニングシートに改良されているものも存在し、波動輸送用として不定期急行・快速や団臨などに使用されてきたが、これらの運用も新車導入に伴い余剰となった特急型485系や183系に置き換えられ2003年までに全車廃車となった。
| 車両番号:モハ166-4(廃車) |
種別・行先:ホリデー快速むさしの号 河口湖 |
収録区間:北朝霞→新秋津 |
| 最高速度:95km/h |
マイク:CM-S330 |
収録日:'00.10.22録音 |
音(YouTube) 10:33  |
デッキでの収録です。国鉄急行型の標準音です。初期の4両のみの、C-1000型CP搭載車での収録です(後期車のCPはC-2000M)。
このページの一番上へ↑
455系
(全廃) |
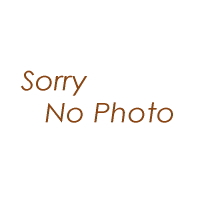 |
| 抵抗・120KW |
| 製造初年:昭和40(1965)年 |
交直両用50Hz用の急行型電車で主に首都圏と東北を結ぶ急行として活躍した。JR化後はJR東日本のみに受け継がれた。東北新幹線の開業により急行運用を失いローカル運用に転用されたが、徐々に719系や701系に押され、晩年は常磐線と東北線(ともに仙台地区)の一部の普通・快速列車に使用されるのみとなっていた。E721系の増備に伴い2008年3月をもって全車運用を離脱し、全廃となった。
| 車両番号:モハ454-50(廃車) |
種別・行先:普通 仙台 |
収録区間:南仙台→長町 |
| 最高速度:90km/h |
マイク:CM-S330 |
収録日:'02.1.1録音 |
| 音(mp3) 3:32 4.85MB |
迫力のある音で頑張っています。太子堂駅開業前の収録です。
このページの一番上へ↑
| 475系 |
 |
| 抵抗・120KW |
| 製造初年:昭和40(1965)年 |
交直両用60Hz用の急行型電車で主に関西と北陸・九州を結ぶ急行として活躍した。山陽新幹線の開業や、北陸本線の急行の特急格上げなどにより急行運用を失い、順次ローカル運用に転用された。JR西日本とJR九州の2社引き継がれ、主に3連で普通列車に使用されていたが、九州のものは817系の増備に伴い、2007年3月を持って定期運用から退き、全廃となった。現在はJR西日本の北陸本線で使用されている。
| 車両番号:クモハ475-36(廃車) |
種別・行先:普通 水俣 |
収録区間:肥後高田→日奈久 |
| 最高速度:95km/h |
マイク:CM-S330 |
収録日:'04.2.18録音 |
| 音(mp3) 5:19 7.31MB |
重厚な走りが楽しめます。現肥薩おれんじ鉄道の区間での収録です。
このページの一番上へ↑
183系
(全廃) |
 |
| 抵抗・120KW |
| 製造初年:昭和47(1972)年 |
房総地区の電化に伴いこの地域にも特急電車を運転することとなり、製造された直流専用特急車。走行距離が短いため食堂車は製造されず、停車駅が多いため2扉となった。その他足回り等は485系とほぼ同一。当初は貫通先頭車の0番台が製造され、房総地区に投入された。その後耐寒耐雪仕様で非貫通先頭車の 1000番台が上越線「とき」181系置き換え用に製造された。その後、上越新幹線開業により「とき」は廃止となり、中央東線に転属し「あずさ」「かいじ」に使用されたが、E351系とE257系の増備に伴い2002年秋をもって撤退した。房総地区のものは255系とE257系500番台に置き換えられ、2005年12月をもって特急運用を失った。特急運用終了後は、波動輸送用として団臨や不定期列車などに細々と使用されていたが、上信越の特急運用を追われた185系に取って代わられ、最後に残ったクハ2両が2015年5月をもって廃車となり、全車廃車となった。
| 車両番号:モハ182-1047(廃車) |
種別・行先:ホリデー快速河口湖4号 大宮 |
収録区間:東所沢→北朝霞 |
| 最高速度:90km/h |
マイク:DR-07 |
収録日:'10.5.2録音 |
音(YouTube) 7:52  |
歯数比は1:3.50とかなりの高速向け。モーターの回転数はかなり低い。モハ183側デッキでの収録です。かなりの爆音車です。
| 車両番号:モハ182-1047(廃車) |
種別・行先:ホリデー快速河口湖3号 河口湖 |
収録区間:北朝霞→新秋津 |
| 最高速度:95km/h |
マイク:DR-2d |
収録日:'10.8.8録音 |
音(YouTube) 11:41  |
こちらは上と逆の、クハ側デッキでの収録です。こちらはずいぶんおとなしい音です。DR-2dでの収録です。
このページの一番上へ↑
| 185系 |
 |
 |
| 抵抗・120KW |
| 製造初年:昭和55(1980)年 |
低迷していた伊豆観光のシェアを取り戻すべく、陳腐化した153系急行「伊豆」を置き換えるため、斬新な塗装で登場した車両。設計当初は特急列車への充当は考えられておらず、あくまで急行型としての設計であり、歯車比は近郊型同様の1:4.82とし、最高速度は110km/hとした。また、普通列車にも使用できるよう幅広ドアを備え、転換クロスシートを装備した。当初の計画通り、急行「伊豆」として運用を開始した。その後、寒冷地用200番台も製造され、こちらは高崎線・信越線方面の急行と「新幹線リレー号」に使用された。その後、急行「伊豆」は特急「踊り子」へ、上信越方面の急行は新特急「谷川」(のちに「水上」へ改称)「草津」「あかぎ」となり、それぞれ特急に格上げされた。また、東北本線の特急「なすの」も設定され、首都圏の特急の主力車両となった。また、ホームライナーも設定された。また、「谷川」の延長運転や臨時特急「そよかぜ」、臨時急行「シュプール号」、臨時快速「信州リレー号」などで新潟県内や長野県内にも顔を出すなど活躍したが、転換クロスシートの室内設備は不評であった。1995年頃から回転リクライニングシート化され、ようやく特急型としての車内設備が整ったが、その頃から長野新幹線開業やスキーブームの終焉に伴う充当列車の削減が行われ、次第に活躍の場が狭まっていった。さらに常磐線を追い出された651系により、宇都宮線・高崎線の特急・ホームライナー運用から撤退したことにより、現在は、現在は伊豆方面の特急「踊り子」、湘南ライナーと波動輸送用のみに使用されており、間合いの普通列車運用もすべて消滅した。また、余剰車の廃車も始まった。今後、E353系増備に伴い中央本線の特急運用を追われたE257系が「踊り子」運用に入ることが決まっており、間もなく特急運用から撤退する見込みとなっている。
| 車両番号:モハ185-20(廃車) |
種別・行先:特急踊り子115号 修善寺 |
収録区間:品川→横浜 |
| 最高速度:110km/h |
マイク:R-09HR |
収録日:'09.5.9録音 |
音(YouTube) 17:01  |
デッキでの収録です。モーター音自体は113系と変わりませんが、ブレーキ緩解音は201系に近い。車輪削正後なのか、速度に対して音がかなり高めです。順調に飛ばしていますが、川崎でハプニング発生です。
| 車両番号:モハ185-227 |
種別・行先:特急あかぎ10号 上野 |
収録区間:本庄→籠原 |
| 最高速度:110km/h |
マイク:DR-2d |
収録日:'10.8.3録音 |
音(YouTube) 12:44  |
デッキでの収録です。DR-2dでの収録です。
| 車両番号:モハ185-8 |
種別・行先:普通 熱海 |
収録区間:二宮→鴨宮 |
| 最高速度:110km/h |
マイク:DR-2d |
収録日:'11.7.21録音 |
音(YouTube) 7:47  |
普通列車運用での走行音。デッキでの収録です。基本7連(4M3T)+付属5連(2M3T)の12両編成(6M6T)の列車での収録で、加速は鈍いですが、国府津→鴨宮では110km/h運転をしています。
このページの一番上へ↑
189系
(全廃) |
 |
| 抵抗・120KW |
| 製造初年:昭和50(1975)年 |
183系1000番台を基本に横軽協調運転用機器を取り付け、特急「あさま」用に製造された車両。その後長野新幹線開通により「あさま」の運用を失った。一部は中央東線や房総地区に転属し、183系と混結するなどして特急運用に就いたが、E351系、E257系などに置き換えられたためこれらの地区の特急運用も失った。6両がジョイフルトレイン「彩野」に改造され、各種イベント列車に使用されたのち、「日光」「きぬがわ」の予備車として東武線にも直通したが、2011年6月をもって運用を失い、廃車となった。晩年は長野6連4本、豊田に6連3本が残され、長野地区では信越本線の定期普通列車に使用されたほか、波動輸送用としても活躍した。その後、長野地区では北陸新幹線の長野~金沢間開業に伴い、信越本線の一部区間がしなの鉄道とえちごトキめき鉄道に移管されたことにより、信越本線の普通列車運用を失い、2015年4月~5月にかけて3本が廃車となった。豊田では、波動輸送運用が上信越の特急運用を追われた185系に置き換えられたことにより2018年1月~4月にかけて3本とも廃車となった。そして、最後に残った長野の1編成が2019年3月のイベント運転を最後に引退し、全車廃車となった。JR東日本のみの在籍であった。
| 車両番号:モハ188-45(廃車) |
種別・行先:ホリデー快速河口湖3号 河口湖 |
収録区間:新座→新秋津 |
| 最高速度:95km/h |
マイク:CM-S330 |
収録日:'06.7.8録音 |
音(YouTube) 7:42  |
足回りは183系と共通のため音は全く同じです。デッキでの収録です。
このページの一番上へ↑
251系
(全廃) |
 |
 |
| 界磁添加励磁・120KW |
| 製造初年:平成2(1990)年 |
陳腐化してきた185系踊り子による伊豆観光輸送の低迷にメスを入れるべく、伊豆急車の「リゾート踊り子」の好評に触発され、設計・製造された特急車。足回りは651系のものを基本に、最高速度を120km/hとし、歯車比を185系と同じ1:4.82とした。2002年に内装を中心にリニューアルが実施され、その際に塗装が変わった。6M4Tの10両固定編成が4本在籍し、「スーパービュー踊り子」のほか、平日のホームライナーにも使用されていた。2020年3月改正で、「スーパービュー踊り子」はE261系「サフィール踊り子」へ、ホームライナーは185系へそれぞれ置き換えられ、251系は運用を失い、全車廃車となった。
| デッキ |
| 車両番号:モハ251-103(廃車) |
種別・行先:特急スーパービュー踊り子10号 大宮 |
収録区間:熱海→湯河原 |
| 最高速度:110km/h |
マイク:DR-07 |
収録日:'10.3.6録音 |
音(YouTube) 5:23  |
モーター音の音程は185系と変わらないようです。4号車デッキでの収録で、扉扱いはありません。
| 客室 |
| 車両番号:モハ251-7(廃車) |
種別・行先:特急スーパービュー踊り子10号 大宮 |
収録区間:熱海→湯河原 |
| 最高速度:100km/h |
マイク:R-09HR |
収録日:'09.5.9録音 |
音(YouTube) 5:21  |
客室での収録です。モーター音の音程は185系と変わらないようです。土曜日夕刻の上り行楽列車ですので、車内環境はあまりよくありません。トンネル内ではなぜか風切音が非常に大きいです。
このページの一番上へ↑
| 255系 |
 |
VVVF(GTO)・95KW
VVVF(IGBT)・95KW |
製造初年:
平成5(1993)年
平成27(2015)年(IGBT機器) |
老朽化した183系0番台の置き換え用として製造された特急車。足回りは209系910番台のものとほぼ同一で主電動機出力95KW、東芝製VVVFインバーター装置を搭載している。歯車比はE217系と同一の1:6.06。4M5Tの9連5本が存在し、「しおさい」「わかしお」「さざなみ」でE257系500番台とともに運用に就いている。これらの特急でグリーン車が連結されているものは255系、連結されていないものはE257系の運用となる。2015年から制御装置の換装が始まり、2016年3月、GTOで残った最後の1編成が更新のため入場し、本形式は全車IGBTとなった。新しい制御装置はE233系近郊型と同等のものとなっている。
| GTO(消滅) |
| 車両番号:モハ255-5 |
種別・行先:特急わかしお10号 東京 |
収録区間:茂原→蘇我 |
| 最高速度:120km/h |
マイク:R-09HR |
収録日:'10.5.7録音 |
音(YouTube) 20:21  |
東芝GTOらしい音です。デッキでの収録です。この車両はIGBT化されました。
| GTO(消滅) |
| 車両番号:モハ255-10 |
種別・行先:特急新宿わかしお 新宿 |
収録区間:大網→蘇我 |
| 最高速度:120km/h |
マイク:DR-2d |
収録日:'14.8.30録音 |
音(YouTube) 13:18  |
こちらは単一指向性マイク×2(X-Y)搭載のDR-2dでの収録です。デッキでの収録で、上で公開しているR-09HR(無指向性マイク×2搭載)で収録した音声と同じ場所での収録です。マイクの比較用にどうぞ。この編成は、現在IGBT化されています。
このページの一番上へ↑
| E257系 |
 |
 |
| VVVF(IGBT)・145KW |
| 製造初年:平成13(2001)年 |
老朽化した183・189系の「あずさ」「かいじ」の置き換え用として製造された特急車。5M4Tの基本編成と1M1Tの増結編成があり、主に「あずさ」は11連、「かいじ」は9連で運用に就いていた。のちに房総地区の183系もこの系列で置き換えることとなり、500番台が製造された。500番台は全車が3M2Tの5連を組み、5連または2本併結の10連で「わかしお」「さざなみ」「しおさい」「あやめ」に使用されている。足回りはE653系のものとほぼ同じで、主電動機出力は145KW。制御装置は0番台がE231系近郊型と、500番台はE531系とほぼ同等となっている。0番台はE353系の増備に伴い2019年3月改正をもって「あずさ」「かいじ」の運用を終了した。廃車はされず、「踊り子」に転用される見込みとなっている。
| 0番台 |
| 車両番号:クモハE257-4 |
種別・行先:特急あずさ9号 松本 |
収録区間:甲府→韮崎 |
| 最高速度:130km/h |
マイク:R-09HR |
収録日:'10.9.13録音 |
音(YouTube) 9:58  |
こちらもデッキでの収録です。R-09HRでの収録です。
このページの一番上へ↑
| E259系 |
 |
| VVVF(IGBT)・140KW |
| 製造初年:平成21(2009)年 |
「成田エクスプレス」用に製造された特急車。従来の253系は、特に老朽化が進んでいたわけではないが、成田空港輸送のイメージアップと新規開業する成田スカイアクセス線に対抗するため、車両を全面的に置き換えることとなった。132両が一気に製造され、2009年10月1日の運転開始から1年も経たない2010年7月1日をもって成田エクスプレス全列車の置き換えを完了した。4M2Tの6両固定編成のみが存在する。当初のダイヤでは、大半が横浜系統と新宿系統をそれぞれ6連で運転、東京~成田空港間は両系統を併結し12連で運転されていたが、現在は分割併合を伴わない運用も増えた。横浜系統は大船発着、新宿系統は池袋、高尾、大宮発着の列車も存在する。足回りはE531系とほぼ同じで、歯車比はE653系と同じ1:5.65となっている。
| 車両番号:モハE258-503 |
種別・行先:特急成田エクスプレス51号 成田空港 |
収録区間:大船→品川 |
| 最高速度:110km/h |
マイク:R-09HR |
収録日:'10.7.21録音 |
音(YouTube) 38:59  |
E531系の非同期音+E653系のモーター音といった音です。客室での収録です。
このページの一番上へ↑
E351系
(全廃) |
 |
VVVF(GTO)・150KW
VVVF(IGBT)・150KW |
| 製造初年:平成5(1993)年 |
高速バスとの競争が激しい「あずさ」のスピードアップを目指して開発・製造された特急車。振り子式を採用、カーブでの走行速度は、本則+25km/hとなり、新宿~松本間は最速2時間25分と、初めて2時間半を切った。愛称は「スーパーあずさ」とし、振り子式でない車両の運用と差別化が図られている。足回りは、量産先行車2本がGTOで、量産車3本はIGBTとなっている。中央線の高速化は計画通りには進まず、振り子車両はこの5本のみで製造が打ち切られ、以降はE257系が製造された。「スーパーあずさ」全列車と一部の「中央ライナー」に使用されてきたが、老朽化に伴い、後継のE353系に置き換えられ、2018年3月改正をもって定期運用から退き、4月のさよなら運転を最後に全車引退した。波動輸送用への転用はされず、全車解体された。
| IGBT |
| 車両番号:モハE351-9(廃車) |
種別・行先:特急スーパーあずさ28号 新宿 |
収録区間:岡谷→茅野 |
| 最高速度:120km/h |
マイク:R-09HR |
収録日:'10.9.13録音 |
音(YouTube) 13:49  |
制御装置は日立3レベルで、非同期音は東武30000系と同じタイプ。モーター音は歯車比16:xのタイプ。外扇タイプで、高速走行時の音は大きい。デッキでの収録です。
このページの一番上へ↑
371系
(全廃) |
 |
| 界磁添加励磁・120KW |
| 製造年:平成3(1991)年 |
御殿場線・小田急線直通「あさぎり」の特急格上げ、相互乗り入れ化に伴いに製造された車両。5M2Tの7両固定編成1編成のみの製造となった。足回りは211系5000番台や6000番台と共通で、歯車比は高速向けの1:4.21とした。「あさぎり」のほか静岡地区のホームライナーにも使用されたが、1編成しかないため、検査時は前者は小田急20000形が、後者は乗車整理券不要の快速に変更の上211系や313系が代走した。「あさぎり」の運転区間と本数の縮小により、2012年3月をもって定期運用から撤退した。同時にJR東海車の小田急乗り入れも中止となった。その後、臨時列車として運用に就いたが、2014年11月をもって最後の運用を終え、全車廃車となった。廃車車両の一部は富士急行に譲渡された。
| 車両番号:クモハ371-101 |
種別・行先:特急あさぎり6号 新宿 |
収録区間:駿河小山→松田 |
| 最高速度:110km/h |
マイク:DR-2d |
収録日:'11.5.20録音 |
音(YouTube) 15:08  |
デッキでの収録です。音は651系内扇車に似ています。この車両は、富士急行に譲渡され、「富士山ビュー特急」として活躍中(クモハ371-101→富士急8501)。
このページの一番上へ↑
| 373系 |
 |
| VVVF(GTO)・185KW |
| 製造初年:平成7(1995)年 |
身延線急行「富士川」の格上げ・置き換え用として製造された特急車。1M2Tの3両固定という身軽な編成で、のちに東海道線・飯田線にも活躍の場を広げた。ドア幅は広く、デッキは仕切扉なしと簡略化され、普通列車、ホームライナーにも使用されている。かつては特急「東海」や夜行快速「ムーンライトながら」、間合い運用の普通列車として東京駅にも姿を見せていた。
| 車両番号:クモハ373-2 |
種別・行先:特急東海4号 東京 |
収録区間:沼津→三島 |
| 最高速度:110km/h |
マイク:CM-S330 |
収録日:'03.3.8録音 |
| 音(mp3) 4:37 6.35MB |
1M2Tの割には加速は結構良い。今は無き特急「東海」での収録です。客室での収録です。
このページの一番上へ↑
| 651系 |
 |
| 界磁添加励磁・120KW |
| 製造初年:昭和63(1988)年 |
常磐線沿線の高速バスへの対抗および老朽化した485系の置き換えのため製造された特急車。JR東日本が設計・開発した初の特急型電車。それまでの鉄道車両にはなかった斬新なデザインは大きなインパクトを与えた。足回りは211系で実績のあるシステムを採用、歯車比を1:3.95と高速向けにし、滑走検知装置を取り付け、在来線で初の130km/h運転を実現した。交流は50Hzのみの対応で、常磐線「スーパーひたち」全列車と一部の「フレッシュひたち」に使用された。音は外扇と内扇の2種。E657系の導入に伴い2013年3月改正をもって常磐線特急の定期運用から撤退した。その後、直流化改造が行われ1000番台とされ、2014年3月改正から「草津」と「あかぎ」「スワローあかぎ」に使用されている。
| 外扇 |
| 車両番号:モハ650-101 |
種別・行先:特急フレッシュひたち55号 土浦 |
収録区間:牛久→荒川沖 |
| 最高速度:120km/h |
マイク:DR-2d |
収録日:'11.3.6録音 |
音(YouTube) 6:30  |
各駅に停車する区間で、客室での収録です。起動時は国鉄急行型に近い音です。外扇は、211系などと同じく、高速域で高音が目立つタイプですが、歯車比が高速向けのため、回転数が低いです。この車両は現在、1000番台化され、高崎線の特急で活躍中です(モハ650-101→モハ650-1001)。
| 内扇 |
| 車両番号:モハ651-10(廃車) |
種別・行先:特急フレッシュひたち13号 勝田 |
収録区間:友部→水戸 |
| 最高速度:130km/h |
マイク:AT9940 |
収録日:'10.4.11録音 |
音(YouTube) 9:49  |
客室での収録です。音程は国鉄急行型とよく似ています。この車両を含む編成は、改造されることなく、廃車・解体されました。
このページの一番上へ↑
| E653系 |
 |
| VVVF(IGBT)・145KW |
| 製造初年:平成9(1997)年 |
651系導入後も半数が485系「ひたち」として残ったが、これを置き換えるため製造された交直両用の特急車両。JR特急車としては初めて交流50Hz、60Hz両対応となった(ただし、現在60Hz区間での定期運用はない)。普通車のみの構成でグリーン車は製造されていない。車体色は5色が存在し、常磐線沿線の名所をイメージしたものとされている。VVVFインバータ制御でモーター出力は145KW。4M3Tの基本編成と2M2Tの付属編成があり、7、11、14連の編成で常磐線特急「フレッシュひたち」に使用された。E657系増備に伴い2013年3月改正をもって常磐線特急から撤退した。基本編成は、羽越本線の特急「いなほ」に転用され、同列車の485系を置き換えた。付属編成は、北陸新幹線と上越新幹線を結ぶ新設の特急「しらゆき」に使用されることとなった。
| 直流区間 |
| 車両番号:モハE653-17 |
種別・行先:特急フレッシュひたち5号 勝田 |
収録区間:柏→取手 |
| 最高速度:110km/h |
マイク:R-09HR |
収録日:'08.11.2録音 |
| 音(mp3) 7:19 10.0MB |
モーター音は名鉄の3100系と同じ。高速域の加速は非常に良い。日立3レベルIGBTで、非同期音は東京メトロ7000系改造車(同仕様車)によく似ている。デッキでの収録です。
| 直流区間 |
| 車両番号:モハE652-18 |
種別・行先:特急フレッシュひたち5号 勝田 |
収録区間:柏→取手 |
| 最高速度:120km/h |
マイク:R-09HR |
収録日:'10.6.13録音 |
| 音(mp3) 7:24 10.1MB |
こちらは客室内での収録です。非同期音はよく聞こえません。
| 直流~交流区間 |
| 車両番号:モハE653-14 |
種別・行先:特急フレッシュひたち49号 土浦 |
収録区間:柏→土浦 |
| 最高速度:130km/h |
マイク:SP-TFB-2 |
収録日:'12.11.10録音 |
| 音(mp3) 29:19 40.2MB |
客室内での収録です。空調は切られていました。
| 交流区間 |
| 車両番号:モハE653-13 |
種別・行先:特急フレッシュひたち48号 上野 |
収録区間:水戸→友部 |
| 最高速度:130km/h |
マイク:DR-07 |
収録日:'10.4.11録音 |
| 音(mp3) 10:50 14.8MB |
交流区間の走行音です。水戸駅出発時に速度制限があり、ストレートに加速していません。デッキでの収録です。
| 交流区間 |
| 車両番号:モハE653-13 |
種別・行先:特急フレッシュひたち48号 上野 |
収録区間:土浦→牛久 |
| 最高速度:125km/h |
マイク:DR-07 |
収録日:'10.4.11録音 |
| 音(mp3) 8:07 11.1MB |
こちらもデッキでの収録です。上と同じ列車の別区間の走行音で、ストレートに加速しています。直流区間に比べ、変調のタイミングが遅い。
| 交流区間 |
| 車両番号:モハE652-18 |
種別・行先:特急フレッシュひたち5号 勝田 |
収録区間:石岡→友部 |
| 最高速度:130km/h |
マイク:R-09HR |
収録日:'10.6.13録音 |
| 音(mp3) 10:49 14.8MB |
客室内での収録。上から2番目のファイルと同じ列車の別区間の走行音です。非同期音はよく聞こえませんが、加速時の変調のタイミングが直流区間より遅いことはよくわかります。
| 交流区間 |
| 車両番号:モハE652-17 |
種別・行先:特急フレッシュひたち44号 上野 |
収録区間:土浦→牛久 |
| 最高速度:130km/h |
マイク:R-09HR |
収録日:'10.6.13録音 |
| 音(mp3) 8:07 11.1MB |
こちらも客室内での収録です。ギアの噛み合わせのせいか、WN車を思わせるような床振動があります(もっともWN車と違い、加減速時にも振動しています)。個体差、というより整備上のことでしょうか…。
| 交流区間 |
| 車両番号:モハE652-20 |
種別・行先:特急フレッシュひたち5号 勝田 |
収録区間:ひたち野うしく→土浦 |
| 最高速度:110km/h |
マイク:DR-2d |
収録日:'11.2.13録音 |
| 音(mp3) 6:56 9.53MB |
2005年に増備された最終編成の走行音です。ドアの開閉時にアナウンスが流れますが、非同期音、走行音とも変化はありません。デッキでの収録です。
このページの一番上へ↑
| E657系 |
 |
| VVVF(IGBT)・140KW |
| 製造初年:平成24(2012)年 |
車齢25年を迎えようとしていた「スーパーひたち」651系の置き換えおよび、いわき以南の特急車両共通化計画により、「フレッシュひたち」E653系を置き換えるため製造された交直両用の特急車両。E653系とは違い、交流区間は50Hzのみの対応となっている。6M4Tの10両固定編成16本が一気に製造され営業開始から僅か1年で651系・E653系を置き換えた。足回りはE259系とほぼ同じで、VVVFインバータ制御でモーター出力は140KW。2013年10月から2015年3月にかけて、「スワローあかぎ」で導入されたスワローシステムを発展させた新しい座席予約システムを搭載する工事が行われ、その際予備車不足から651系の運用が一部復活した。その後、上野東京ライン開業により品川駅に乗り入れるようになり、その運用増に対応して1編成が増備され、現在は10連17本が在籍する。同時に新しい座席予約システムが稼働を開始し、「スーパーひたち」は「ひたち」、「フレッシュひたち」は「ときわ」と名を変え、本形式が全列車を担当し、活躍中。
| 交流区間 |
| 車両番号:モハE656-4 |
種別・行先:特急ときわ51号 高萩 |
収録区間:石岡→水戸 |
| 最高速度:130km/h |
マイク:SP-TFB-2 |
収録日:'16.11.6録音 |
音(YouTube) 23:16  |
E259系と同じ音です。ただし、交流区間なので、変調のタイミングが遅くなっています。この時は、赤塚駅手前で先行の普通列車に追いついてしまい、信号に引っかかりながらのんびり走ります。
このページの一番上へ↑
| キハ40系 |
 |
220ps
330ps |
| 製造初年:昭和52(1977)年 |
国鉄末期に地方交通線用として製造された系列。2扉デッキ付きのキハ40(両運転台)、キハ48(片運転台)、デッキ無しでやや中央に寄った両開き扉を持つセミクロスシート車キハ47系の3形式がある。JR旅客鉄道全6社に在籍する。各社でエンジン換装、冷房化等の更新工事が実施されている。
| 車両番号:キハ47-121 |
種別・行先:普通 佐賀 |
収録区間:鬼塚→山本 |
| 最高速度:70km/h |
マイク:CM-S330 |
収録日:'04.2.17録音 |
| 音(mp3) 4:38 4.25MB |
重厚な走りが楽しめます。この車両は現在エンジン換装が行われ、車番が変更されています(キハ47-121→キハ47-8121)。
このページの一番上へ↑
| キハ58系 |
 |
180ps×2
180ps |
| 製造初年:昭和36(1961)年 |
国鉄急行型ディーゼルカーのスタンダードとして大量に増備された形式。普通車2エンジン車キハ58、1エンジン車キハ28、グリーン車2エンジン車キロ 58、1エンジン車がキロ28が製造された。その後改造によりキロハ28が生まれている。気動車急行の代表として大活躍したが、急行列車の削減に伴い順次ローカル運用に転用された。JR旅客鉄道6社のうちJR北海道を除く5社に継承されたが老朽化のため廃車が進んでおり、JR東海、JR西日本、JR四国、JR九州ではすでに全廃、現在も運用に入っているものはJR東日本の在籍車はジョイフルトレイン「kenji」のみとなっている(こちらも定期運用はない)。廃車車両の一部はロシア(サハリン)・タイ・ミャンマーに無償譲渡された。また、2012年に1両がいすみ鉄道に譲渡され、キハ52とともに運用に就く見込みである。
| 車両番号:キハ58-1520(廃車) |
種別・行先:普通 大館 |
収録区間:渋民→好摩 |
| 最高速度:90km/h |
マイク:CM-S330 |
収録日:'02.1.1録音 |
| 音(mp3) 4:50 6.64MB |
大雪の中を頑張るキハ58の音です。キハ58×2両の編成で、加速がかなり良かったような気がします。
このページの一番上へ↑
| キハ11系 |
 |
| 330ps |
| 製造初年:平成元(1989)年 |
JR東海の軽快ディーゼルカー。ワンマン設備を備えており、JR東海の非電化区間ローカルの主力として活躍している。武豊線と高山線白川口以北の運用はないが、それ以外の非電化区間の主力として活躍中。
| 車両番号:キハ11-121 |
種別・行先:普通 多治見 |
収録区間:鵜沼→坂祝 |
| 最高速度:90km/h |
マイク:CM-S330 |
収録日:'03.2.19録音 |
| 音(mp3) 5:12 4.76MB |
軽やかな走りです。
このページの一番上へ↑