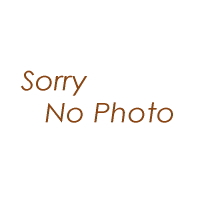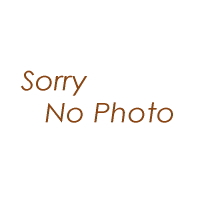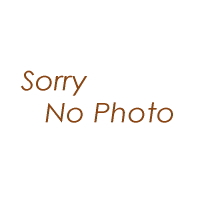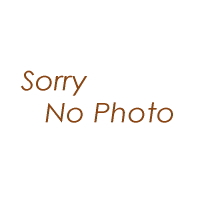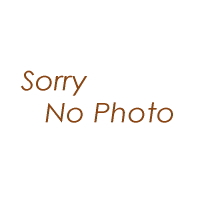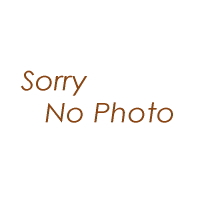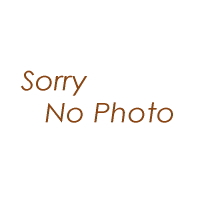近鉄・京都市営地下鉄の走行音
・近鉄
3220系 5200系 8810系 6600系 8600系 8400系 6200系 1000系
・京都市営地下鉄
10系
| 近鉄3220系 |
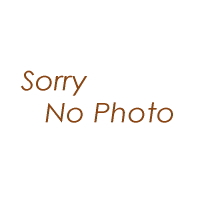 |
| VVVF(IGBT)・185KW |
| 製造初年:平成12(2000)年 |
次世代通勤車「シリーズ21」のトップを切って落成した京都市営地下鉄乗り入れ対応車。「シリーズ21」の中では唯一他車との併結を行わないため、前面貫通扉は持たず、車掌側にオフセットされた非常口を持つ。純電気ブレーキも採用された。6連3本が製造されたが所用数に達しているためか増備されず、他車との併結ができる9820系や6820系などが続々と増備されている。
| 車両番号:3221 |
種別・行先:普通 国際会館 |
収録区間:寺田→久津川 |
| 最高速度:80km/h |
マイク:CM-S330 |
収録日:'02.11.20録音 |
| 音(mp3) 1:48 2.49MB |
日立らしい非同期音です。
このページの一番上へ↑
| 近鉄5200系 |
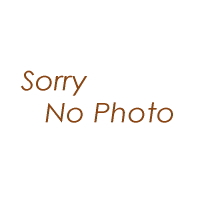 |
| VVVF(GTO)・165KW |
| 製造初年:昭和63(1988)年 |
長距離急行や団体用に製造された3扉転換クロスシート車。足回りは1420系列と同じ。その後マイナーチェンジにより5209系・5211系が登場したがモーターは同じ。ただし、歯車比は最初の4編成が1:6.31、それ以降は1:5.73と異なっている。ロングシートの一般車2両を併結し、6両編成として上本町・名古屋~伊勢市・鳥羽間の急行を中心に使用されている。
| 歯車比1:6.31 |
| 車両番号:5202 |
種別・行先:急行 松阪 |
収録区間:伊勢若松→白子 |
| 最高速度:110km/h |
マイク:CM-S330 |
収録日:'01.2.15録音 |
| 音(mp3) 4:05 3.74MB |
都営5300形(初期型・ソフト未変更車)にそっくりな音。
このページの一番上へ↑
| 近鉄8810系 |
 |
| 界磁チョッパ・160KW |
| 製造初年:昭和56(1981)年 |
大阪・名古屋線の1400系とともに京都・奈良線に投入された界磁チョッパ車。前面モデルチェンジ車である。モーターは強力160KW。近鉄では界磁チョッパの時代は長くはなく、それほど増備されることなくVVVF車に受け継がれた。
| 車両番号:8822 |
種別・行先:普通 西大寺 |
収録区間:向島→小倉 |
| 最高速度:90km/h |
マイク:CM-S330 |
収録日:'02.11.20録音 |
| 音(mp3) 2:43 3.75MB |
8400系・8600系に比べ、静かで高速域の加速は良くなっている。
このページの一番上へ↑
| 近鉄6600系 |
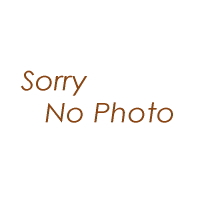 |
| 界磁チョッパ・150KW |
| 製造初年:昭和58(1983)年 |
南大阪線の界磁チョッパ4扉ロングシート車。わずかに8両の存在である。主に5連の各停、準急の増結用として運用されている。
| 車両番号:6604 |
種別・行先:普通 藤井寺 |
収録区間:恵我ノ荘→高鷲 |
| 最高速度:70km/h |
マイク:CM-S330 |
収録日:'00.12.26録音 |
| 音(mp3) 1:46 1.01MB |
小田急8000形チョッパ車に似た音です。
このページの一番上へ↑
| 近鉄8600系 |
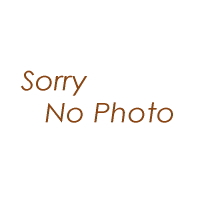 |
抵抗・145KW
界磁位相・145KW |
| 製造初年:昭和48(1973)年 |
8400系の増備車で奈良・京都線用4扉ロングシート車である。更新工事により、回生ブレーキ付き界磁位相制御に変更された編成がある。この際4連はMc車とT車の位置を入れ替えている。
| 界磁位相 |
| 車両番号:8601 |
種別・行先:普通 西大寺 |
収録区間:大久保→久津川 |
| 最高速度:65km/h |
マイク:CM-S330 |
収録日:'00.12.25録音 |
| 音(mp3) 1:51 1.07MB |
渋い音です。発車時に空転しています。
| 抵抗 |
| 車両番号:8607 |
種別・行先:普通 西大寺 |
収録区間:久津川→寺田 |
| 最高速度:75km/h |
マイク:CM-S330 |
収録日:'00.12.26録音 |
| 音(mp3) 1:51 1.06MB |
こちらも渋い音です。
このページの一番上へ↑
| 近鉄8400系 |
 |
抵抗・145KW
界磁位相・145KW |
| 製造初年:昭和44(1969)年 |
8000系の増備車で奈良・京都線用4扉ロングシート車。近年更新工事が進められており、回生ブレーキ付き界磁位相制御に変更された。この際4連はMc車とT車の位置を入れ替えている。
| 抵抗 |
| 車両番号:8455(廃車) |
種別・行先:普通 京都 |
収録区間:新祝園→狛田 |
| 最高速度:100km/h |
マイク:CM-S330 |
収録日:'02.11.20録音 |
| 音(mp3) 2:32 3.49MB |
大変渋い音です。スピードを出したときの高音も迫力があります。
このページの一番上へ↑
| 近鉄6200系 |
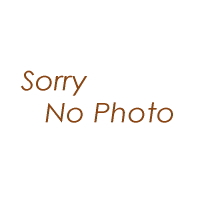 |
| 抵抗・135KW |
| 製造初年:昭和49(1974)年 |
南大阪線の4扉ロングシート車6000系の増備車。足回りは6000・6020系と共通。モーター出力は標準軌線用よりもやや抑え目。
| 車両番号:6209 |
種別・行先:普通 藤井寺 |
収録区間:針中野→矢田 |
| 最高速度:80km/h |
マイク:CM-S330 |
収録日:'00.12.26録音 |
| 音(mp3) 1:43 0.99MB |
特に特徴のない音です。
このページの一番上へ↑
| 近鉄1000系 |
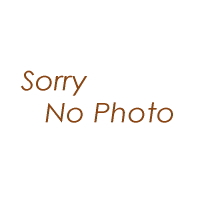 |
| 抵抗・125KW |
製造初年:
昭和47(1972)年(車体)
昭和34(1959)年(機器) |
旧型車の車体更新車で、廃車された800系・1600系の主電動機を流用して高性能化された通勤車。抑速ブレーキは無く、青山峠越えはできない。全車名古屋線で運用されている。機器の老朽化に伴い、廃車が開始されている。
| 車両番号:1003(廃車) |
種別・行先:準急 四日市 |
収録区間:近鉄弥富→近鉄長島 |
| 最高速度:90km/h |
マイク:CM-S330 |
収録日:'01.2.15録音 |
| 音(mp3) 3:32 2.02MB |
木曽川を渡ります。特に特徴のないモーター音です。
このページの一番上へ↑
| 京都市交10系 |
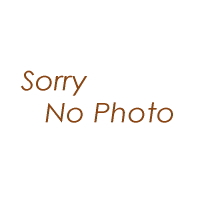 |
| 電機子チョッパ・130KW |
| 製造初年:昭和55(1980)年 |
京都市営地下鉄開業時から活躍する4扉ロングシート車。当初は近鉄京都線新田辺まで、現在は近鉄奈良まで直通運転を行っている。
| 車両番号:1713 |
種別・行先:普通 新田辺 |
収録区間:久津川→寺田 |
| 最高速度:80km/h |
マイク:CM-S330 |
収録日:'01.11.20録音 |
| 音(mp3) 1:52 2.56MB |
チョッパ音は低め。
このページの一番上へ↑